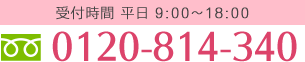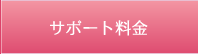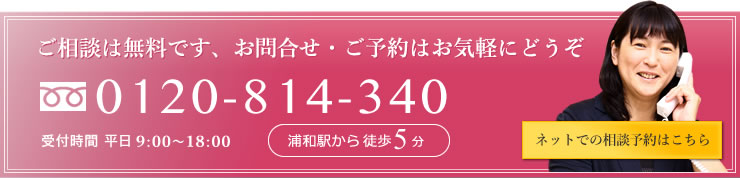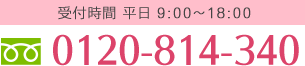解決事例~特別縁故者の申立/埼玉浦和で相続のご相談
状況
息子さんが亡くなられてご両親が相談に来ました。
この息子さんには内縁の妻がいて、お二人にお子さんはおりませんでしたが、彼女の連れ子がいました。約15年、同棲していました。
ご相談者のご両親は内縁の妻への感謝の念を強く語り、内縁の妻もその子供たちも本当のお嫁さんとお孫さんのように思っていたことから、「自分たちは相続を放棄して、内縁の妻に相続させたい」というご相談でした。
対応
ご両親の相続への想い
内縁の妻に今まで通り生活してほしいという思いからの相続放棄でしたが、相続放棄は相続が開始してから3ヶ月以内に手続きが必要となり、相談に来た時点でその期限間近でした。
被相続人の両親はご健在であり、通常であれば相続人は両親のみです。
ご両親の想い等を含め、内縁の妻が相続するには「内縁の妻が特別縁故者」になり得るか。ということが論点でした。
特別縁故者の申立
① まず亡くなった方が居住していた住所地を管轄する家庭裁判所に、相続財産管理人の専任の申立をします。選任されると官報で公告されます。
② 本当に相続人がいないか、捜索の広告を行います。その期間は6ヶ月以上です。
もしその期間満了までに相続人であるという人が現れないと、相続人は“存在しない”という判断がなされます。
③ その相続人がいないという判断がなされてから、3ヶ月以内に特別縁故者の申立を行います。申し立ては3ヶ月以内と決まっているので注意が必要です。
このように特別縁故者の申立も一定期間を必要とします。
そして、例え申立が認められても遺産のすべてが手に入るわけではなく、被相続人と特別縁故者の関係性、繋がり、諸事情を裁判所が判断して、財産分与の額を決定します。
ご相談者様へこのような手続きを踏むことになると説明した時点で、時間と心労を考えるとこの決断は踏み切れないと考えを改める意思を伝えてくれました。
その後実際に相続すべきご両親へ相続をして、申告手続きを行いました。
まとめ
相続の諸々の手続きは期限が決まっています。
申告は10ヶ月以内。相続放棄は3ヶ月以内。
亡くなった方の希望は分かりませんので、相続人が法に則って手続き・申告をするしかありません。しかし、亡くなる前に遺言書を残しておけば、今回のように特別縁故者の申立をする、しないという話にはならなかったでしょう。
遺言書の必要性を改めて感じたご相談でした。
その他の事例はこちら→【解決事例】
相続のご相談なら地元の身近な相続専門家、埼玉あんしん相続相談室にご相談ください。
さいたま市浦和区、JR浦和駅北口徒歩5分。
お問い合わせはこちら→【埼玉あんしん相続相談室 お問い合わせメールフォーム】
フリーダイヤル0120-814-340 ◆受付9:00~18:00
解決事例の最新記事
- 相続解決事例~分割協議が申告期限までに間に合わなかったケース
- 相続解決事例~二次相続を考慮していなかったA家のケース
- 相続解決事例~相続財産の種類が多い相続
- 相続解決事例~名義預金は相続人が知らないこともある
- 相続解決事例~基礎控除ギリギリでも申告をしたい相談者
- 解決事例~相続した土地を譲渡。譲渡所得の申告と相続税の申告
- 解決事例~路線価が設定されていない宅地の評価|埼玉浦和で相続のご相談
- 解決事例~相続する土地に私道がある/埼玉浦和で相続のご相談
- 解決事例~相続税で注目される名義預金/埼玉浦和で相続のご相談
- 解決事例~遺産分割協議にない財産/埼玉浦和で相続のご相談
- 解決事例~相続が発生!遺言書があったのに・・/埼玉浦和で相続のご相談
- 解決事例~寄与分について兄弟間のトラブル/埼玉浦和で相続のご相談
- 解決事例⑩居住用の不動産はどこ/埼玉浦和で相続のご相談
- 解決事例⑨贈与税と相続税/埼玉浦和で相続のご相談
- 解決事例⑧生前対策/埼玉浦和で相続のご相談
- 解決事例⑦相続放棄/埼玉浦和で相続のご相談
- 解決事例⑥現金が増えていく/埼玉浦和で相続のご相談
- 解決事例⑤複雑な不動産/埼玉浦和で相続ご相談
- 解決事例④弟の相続/埼玉浦和で相続ご相談
- 解決事例③生前贈与/埼玉浦和で相続ご相談
- 解決事例②財産の現金化/埼玉浦和で相続ご相談
- 解決事例①遺産分割協議/埼玉浦和で相続ご相談